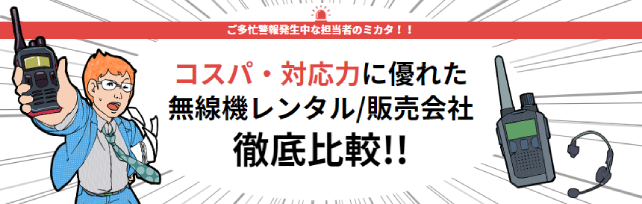医療機関や福祉施設で大活躍する無線機
医療・福祉編
災害時の通信手段は?緊急時の避難に用意しておきたい無線機器
医療機関や福祉施設での業務連絡は、通常PHSで行うと思います。作業員の全員がPHSを持ち、状況に応じて連絡を取るという形が一般的かと思いますが、医療機関や福祉施設でも一部の業務で、あるいは災害時の備えとして無線機を導入しておくと便利・安心なケースがあります。そこで今回は医療機関や福祉施設に導入しておきたい、業務連絡用の無線機を紹介したいと思います。
導入事例
 手術や回診、区切られた環境でもスムーズな通話が可能
手術や回診、区切られた環境でもスムーズな通話が可能
医療・福祉の現場でも無線機は活躍しています。例えば医療機関においては、手術室と外部の連絡手段をハンズフリーのヘッドセットを使った無線で行ったり、福祉施設においては脱走者の捜索をトランシーバーで連絡を取りながら行ったりと、さまざまな業務での使用が想定されます。また、人命を預かる医療、福祉関連の施設には、災害時の対応としてトランシーバーを設置しておくと安心です。
災害時には無線機が活躍する
医療機関、福祉施設においてスタッフの連絡手段として使われている携帯電話やPHSもある意味で無線機の一種。普段からすでに医療や福祉の現場で無線機が使われているとも言えるのですが、大規模な医療機関や福祉施設においては、トランシーバーなどの無線機を導入しておいた方が安心だといえます。
例えば大規模な災害が発生すると、携帯電話は局地的に通信が集中するため、回線が混雑して使用ができなくなります。PHSに関しては携帯電話よりも災害に強いとは言われていますが、一糸乱れずに団体での避難が求められるようなケースでは、スタッフ同士が一斉に情報を共有できる確実な連絡手段が必要となります。そのような場面でトランシーバーなどの無線機を各所に配備しておくと、災害時でもスタッフ同士で自由にコミュニケーションが取れるようになるのです。スタッフのみならず、入院患者や入所者の命を救う連絡手段にもなります。
デジタル簡易無線機が現実的な選択肢
無線機にはいろいろと種類があり、その違いによって免許の有無、登録の有無、出力の大きさ、通信範囲の広さ、通信の安定度などが決まってきます。中には免許も登録も不要で、今すぐ利用が可能な特定小電力無線機もあれば、簡易業務用無線のように業務用に用途が限定されていて、無線従事者の有資格者を配置するよう求められる無線もあります。
医療機関や福祉施設においては、導入のハードルがそれほど高くなく、使い勝手に優れたデジタル簡易無線などの導入が想定されます。総務省に申請登録をするだけで気軽に利用がスタートできる上に、出力が最大5Wとパワフルですので、大きな病院や福祉施設であっても、施設全体でスタッフが同時進行で通信を行えるようになります。
業者を交えて、幾つかの機器を試してみる
ただ、医療機関や福祉施設においては、無線機の導入には慎重になる必要があります。無線機の電波が、医療機器などに影響を及ぼし、誤作動などを起こす恐れがあるからですね。導入にあたっては、専門の業者に十分に相談をしてください。
また、災害時などを想定して無線機を導入する場合は、実際に一度、機器をレンタルして、自分たちの医療機関や福祉施設で試験的に利用する必要があります。導入を予定する無線機の出力で自分たちの施設がカバーできるのなども、十分にチェックしてください。

- 規模
- スタッフ数名規模のクリニックではなく、大規模な総合病院が想定されます。また、敷地内に何棟も施設が建ち並ぶ大型の福祉施設などでも、災害時に備えて導入が望まれます。
- 主な使用場所
- 病院や福祉施設の建物内部、地下、屋上。さらには敷地内での利用が想定されます。
- 無線機の利用者数
- 手術室の各スタッフに配置したり、各病棟のナースステーションに配備したりするなど、施設の状況に合わせて導入してください。避難訓練などでは、実際に無線機を利用して訓練を行ってください。
- おすすめ機種
- 大規模な医療施設や大型の福祉施設では、デジタル簡易無線が望まれます。
- 無線機を使うことのメリット
- 災害時に携帯電話やPHSが不通になっても、スタッフ同士の連絡手段を確保できるようになります。また、医療機関においては手術などの作業で、スタッフ間の連携がよりスムーズになります。
- 無線機を使った際の注意点
- 普段から無線機の練習をしておかないと、いざというときに使い方が分からない、チャンネルが合わない、バッテリーが切れていた、無線機が壊れていたなどのトラブルが起きる可能性があります。避難訓練などのタイミングで、確認をしておきたいです。
- レンタルと購入の想定予算比較
- デジタル簡易無線機は出力の大きさによって1台2~5万円などさまざまな価格帯で販売されています。レンタルは1台、2,000~5,000円などさまざまです。まずは業者を交えてレンタルで何台か試験的に導入をしてみてください。
- まとめ
- 普段の業務連絡は携帯電話やPHSでも構いませんが、人命を預かる医療機関や福祉施設においては、災害時の緊急連絡手段として無線機の導入が望まれます。
| コスパと対応力に優れた 無線機レンタル会社無線機&トランシーバーのレンタル料金 比較 | ||
|---|---|---|
| 急な状況で無線機の準備が必要になった場合でも、コストパフォーマンスが良く、迅速に対応してくれる会社を選択することをおすすめします。 ここでは、Google検索にて「無線機 レンタル」と検索して公式サイトが表示された74社の無線機レンタル会社の中から「全国対応」「当日出荷に対応」「現地納品に対応」「HPでレンタル料金が明確」「無線機のレンタルをメイン事業としている、もしくは専用サイトを持っている」という条件を満たしている無線機のレンタル会社を選定して紹介してます。(2024年2月8日調査時点) |
||
| 6泊7日のレンタル最安値が980円!! | 用途によって選べる4つのプランを提供 | 365日深夜の受付にも対応 |
| インカム.com | レントシーバー | ネクストギアーズ |
 引用元:インカム.com公式HP 引用元:インカム.com公式HP(https://www.incom-rental.com/) |
 引用元:レントシーバー公式HP 引用元:レントシーバー公式HP(https://www.rentceiver.jp/) |
 引用元:ネクストギアーズ公式HP 引用元:ネクストギアーズ公式HP(https://www.next-gears.net/) |
|
公式サイトを 見る |
公式サイトを 見る |
公式サイトを 見る |
| コスパと対応力に優れた 無線機レンタル会社無線機&トランシーバーの レンタル料金 比較 |
||
|---|---|---|
| 急な状況で無線機の準備が必要になった場合でも、コストパフォーマンスが良く、迅速に対応してくれる会社を選択することをおすすめします。 ここでは、Google検索にて「無線機 レンタル」と検索して公式サイトが表示された74社の無線機レンタル会社の中から「全国対応」「当日出荷に対応」「現地納品に対応」「HPでレンタル料金が明確」「無線機のレンタルをメイン事業としている、もしくは専用サイトを持っている」という条件を満たしている無線機のレンタル会社を選定して紹介してます。(2024年2月8日調査時点) |
||
| 6泊7日のレンタル最安値が980円!! | ||
| インカム.com | ||
 引用元:インカム.com公式HP 引用元:インカム.com公式HP(https://www.incom-rental.com/) |
||
| 公式サイトを見る | ||
| 用途によって選べる4つのプランを提供 | ||
| レントシーバー | ||
 引用元:レントシーバー公式HP 引用元:レントシーバー公式HP(https://www.rentceiver.jp/) |
||
| 公式サイトを見る | ||
| 365日深夜の受付にも対応 | ||
| ネクストギアーズ | ||
 引用元:ネクストギアーズ公式HP 引用元:ネクストギアーズ公式HP(https://www.next-gears.net/) |
||
| 公式サイトを見る | ||